音楽を自由に使える場合もあるの?

さっき、CDをつくる時には「著作権」の手続きが必要っていうのは、分かったんだけど、家でCDに入っている音楽を別のCDにコピーする時にも著作権が関係するの?
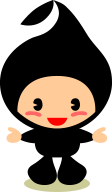
音楽をコピーする時には、原則として著作権を持っている人の許可が必要だよ。でも、自分で聴くために家でコピーする時も、いちいち許可をとらなくてはいけないことになると、大変だよね。
そこで、著作権法では家庭内でのコピーなど、「著作権を持っている人たちの権利にあまり大きな影響を与えないような範囲」で音楽を使う場合には、権利を制限して、音楽を自由に使えるようにしているんだ。

でも、コピーによってできたCDをクラスのみんなに配るのはマズイんだよね?
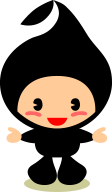
そうだよ。あくまでも、自分や家族が聴くためにコピーするのであれば許可をとる必要がないけれど、他人のためにコピーしたものを配る場合には、著作権をもっている人の許可が必要なんだ。
法律で定められた条件を満たせば、「図書館などでの複製」、「引用」、「学校における複製」など著作権を持っている人の許可をとらないで「自由に使える」場合があります。
営利を目的としないコンサートやイベントでの演奏や上映
大勢の人の前で歌ったり、演奏する場合でも著作権の手続きをとらないで自由に使える場合があります。具体的には、以下の3つの条件にすべてあてはまる場合には、手続きは必要ありません。
逆に言うと、3つの条件のうち1つでも該当しない場合には、著作権の手続きが必要になります。
1.営利を目的としていない

- ※株式会社や商店会などが主催するコンサートは入場料をとらなくても営利目的とみなされることがあります
2.どんな名目でもお金などの入場料をとらない

3.演奏する人(歌手やバンド)にギャラ(報酬)の支払いがない(著作権法38条)

CDのコピー
自分や家族が聴くためにCDを別のCDなどにダビングする場合には、著作権の許可はいらないことになっています。(著作権法30条「私的使用のための複製」)
しかし、デジタル方式の機械だとキレイな音を楽しむことができるので、どんどんコピーしてオリジナルのCDに近い音質で楽しむ人が増えたら、「音楽をつくる人」たちが困ってしまいますよね。
そこで、オーディオ用CD-Rなどデジタル方式で録音できる機械やディスクを使ってダビングをする場合には、作詞家、作曲家、レコード会社、ミュージシャンなどに補償金を支払う制度がつくられています。
補償金は、録音するたびに支払いをするのがむずかしいので、機器やディスクを買う時の代金に上乗せして、まとめて支払うようになっています。この制度を「私的録音補償金制度」といい、デジタル方式の録画についても同じような制度(私的録画補償金制度)があります
。
詳しくはこちらのページを見てください。
タダだから著作権は関係ない?
学校の文化祭ライブを録音した音源をCDにして無料で配る
合唱部の練習のために楽譜を一部だけ買って、コピーして部員に配る
個人のホームページでCDからコピーした音楽を流す
「営利目的じゃないしタダだから、著作権は関係ない。」
と誤解されていることが多いようです。
しかし、上にあげた例はすべて、著作権の手続きが必要なケースになります。
最近では、パソコンやスキャナーなどのデジタル機器が身近になって、「ホンモノ」とほとんど同じコピーが簡単に作れるようになりました。
しかし、CDからコピーしたMP3などの音楽ファイルをタダだからといって、勝手にホームページで流したり、交換できるようにすると、誰でも簡単にダウンロードできてしまうよね。
その結果、商品として売っているCDが売れなくなったりしたら、作詞家・作曲家、レコード会社、ミュージシャンなど「音楽をつくる人」は新しい作品を発表することが難しくなって、私達が気軽に音楽を楽しむことができなくなるかもしれません。
インターネットやパソコンなど音楽を楽しむための道具は増えたけれども、苦労して音楽をつくっている人のことを考えて、「音楽はタダじゃない」ということを忘れないようにしよう。
著作権を侵害すると?
違法にコピーしたCD(海賊版)を販売するなど著作権を侵害する行為については、民事上や刑事上の責任が法律で定められています。
民事上の責任としては、無断で使った分の損害賠償の責任などを負うことになります。刑事上の責任としては、「10年以下の懲役、又は1000万円以下の罰金」という罰則規定が定められています。(法人の場合の罰金は3億円以下です)
損害賠償や罰則と聞くと、「音楽を使う」ことが大変なことだと感じられるかもしれません。しかし、苦労して音楽をつくっている人たちのことを考えて、自分だったらしてほしくないことをしないようにすることが、「著作権を守る」ことにつながるんだ。





