|
私が仕事を始めた70年代には、シンガー・ソングライターという形で活動している人は、ポップミュージックの世界ではほとんどいなかったですね。フォークの先輩はいましたけれども。「シュガー・ベイブ」を始めた頃は「はっぴいえんど」の大瀧詠一さんによく面倒をみていただきました。当時の音楽界というのは、芸能プロダクションがあって、そこに所属することが出発点という感じだったんですが、そういうところではない、すべてが素人集団の事務所から始めた経緯があります。
いわゆる、洋楽で育った世代だったので、自分たちが聴いてきた音楽をベースにオリジナルをつくるという。ですからシンガー・ソングライターという存在自体がサブカルチャーだったわけです。現在の音楽シーンで活躍するアーティストは、ほとんどがシンガー・ソングライターですし、それが主流と言ってもいいと思いますが、私は今でも「自分のやっていることはサブカルチャーだ」という思いがあります。ただ、私たちの“サブカル的な感情”を受け継いでいると感じる人は、今のアーティストの中では、ごく僅かですね。
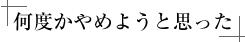
30年の間には、それは何度かやめようと思ったことはありますよ。活動を始めた初期の頃、いいオリジナルがありながら、シングルを売るためには自分の曲を歌えないというような仲間を見ていて、「結局そういうこと?」っていう。音楽が商品であるっていうことが理解できなかったんですね、若かったですし(笑)。私自身のことでは、レコード会社を変わった時に「売れるアルバムを作ってね」と言われて、それまではセルフプロデュースだったんですが、外部のプロデューサーをつけられて、何度も詞や曲を書き直させられました。そうすると、どんどん作品が自分から離れていってしまうような気持ちになって、「もうやめちゃおうかな」と思ったこともありました。もちろん音楽が嫌いになったわけではなくて、ですが。でもその経験は、後に他の歌手に楽曲提供することに繋がりましたし、書き直させられた自分の曲は、今でも歌い続けているスタンダードな曲になりました。80年代にはアイドルも含め、ずいぶん書きました。歌詞だけ、曲だけ、というものも含めれば、100曲以上になります。以前は発注される時、たとえば、参考になるレコードとか歌詞のイメージを具体的に伝えてくれるプロデューサーが普通だったんですが、今は「おまかせ」というのが多くて。それが一番困ります。いずれにしても依頼された仕事はできるだけ受けるようにしています。そうでないと、また「やめちゃおうかな〜」っていうのが・・・・(笑)。
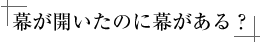
アコースティック・コンサートを始めたのも、ひとつのチャレンジでしたね。87年当時、クラシックの方しかステージに立てなかったサントリーホールでやってみないかというお話をいただいて。最初は「自分には無理かなあ」と思ってお断わりしようとも考えたんですが、仕事って多分「この人ならできるだろう」という前提があって頼んでくるわけですから、その時点では50%やれる可能性があるわけです。それを成功させるかどうかは、あと50%の自分の力なわけで。それならやってみるべきだと、お受けいたしました。それまでずっとポップス路線のバンドでやっていたわけですから、弦のカルテットをバックに最小限の音響システムで歌うというのはとても怖かった。それでも回を重ねるごとに、特に歌に関しては得るところが多くて、現在まで続いています。
でも、コンサートは未だに苦手です。30年もやっているというのに。
20代から30代のはじめまでは、ステージに出てから引っ込むまで緊張の連続で、コンサートが終わっても食事が喉を通らないほどでしたから。客席と自分の間に見えない幕が下りていて、自分の声がお客さんに届かないっていう感覚があったんです。
それが、40歳を過ぎたある日のステージで、突然幕がなくなった。それはびっくりしました。理由は未だにわかりませんが、やっと歌が歌えるようになったんだという思いでした。
最近は自分のアルバムでもシンセをあまり使わず、バンドによる録音を大切にしています。
若い頃は声に張りやのびはあるんですが、声の中の情報量は少ないんです。お年寄りと若者では、一言の言葉の重みが違うように。年を重ねると声の中の情報量が増えるんですね。そうするとシンセやコンピュータ音楽の中だけでは、なんだか歌だけが浮いてくるんです。生楽器というのはやはり情報量が多いですから、その中で歌う方がおさまりがいいんです。

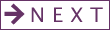
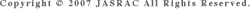
|